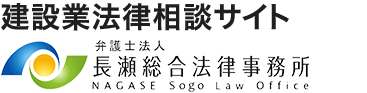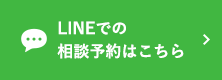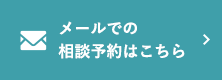2025/09/26 コラム
建設工事の請負代金が支払われない!回収までの3ステップ
はじめに
建設業界において、工事を完成させ、目的物を引き渡したにもかかわらず、施主(注文者)から請負代金が支払われないというトラブルは、残念ながら後を絶ちません。代金の未払いは、建設業者の経営に深刻な影響を与え、資金繰りの悪化や、ひいては下請業者への支払遅延など、さらなる問題を引き起こす原因ともなり得ます。
多くの建設業者の皆様が、日々の業務に追われる中で、このような代金回収の問題に頭を悩ませていらっしゃることでしょう。「施主が何かと理由をつけて支払ってくれない」「催促しても無視される」といった状況で、泣き寝入りしてしまっているケースも少なくないかもしれません。
しかし、正当な仕事に対する対価である請負代金は、必ず回収すべき重要な権利です。本記事では、建設工事の請負代金が支払われない場合に、法的に権利を実現するための具体的な回収ステップを3段階に分けて解説します。この記事をお読みいただくことで、いざという時に冷静かつ的確に行動するための知識を身につけていただければ幸いです。
Q&A
Q1: 施主が「工事に不満がある」「欠陥(契約不適合)がある」と言って支払いを拒否しています。どうすればよいですか?
まず重要なのは、契約書、設計図書、仕様書などに基づき、契約内容通りの工事が完成していることを客観的な証拠で示すことです。施主が主張する「不満」が、単なる主観的なものなのか、法的に「契約不適合」と評価されるものなのかを見極める必要があります。もし契約不適合が存在する場合でも、施主の権利はまず修補(追完)を求めることであり、その程度に応じて代金減額で対応すべき問題です。建物の使用に支障のない軽微な契約不適合を理由に、代金全額の支払いを拒否できる正当な理由にはならないケースがほとんどです。一方的な支払拒否に対しては、まずは書面で契約内容の履行を証明し、支払いを請求することが第一歩となります。
Q2: 何度電話で催促しても無視されます。すぐに裁判を起こした方がよいのでしょうか?
裁判(訴訟)は、債権回収のための強力な手段ですが、時間と費用がかかる側面もあります。そのため、直ちに訴訟を提起するのではなく、その前段階の手続きを検討することが有効です。具体的には、弁護士名で「内容証明郵便」を送付し、支払いを強く催告する方法があります。これは法的に「催告」と評価され、時効の完成を6か月間猶予させる効果があります。これにより、相手方に心理的なプレッシャーを与え、支払いに応じるケースも少なくありません。それでも支払いがない場合には、「支払督促」や「民事調停」といった、訴訟よりも簡易で迅速な裁判所の手続きを利用することも選択肢となります。事案の性質や相手方の態度に応じて最適な手段を選択することが重要です。
Q3: 債権回収を弁護士に依頼すると、費用が高くついて費用倒れにならないか心配です。
弁護士費用がご心配になるお気持ちはよく分かります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、ご依頼いただく前に、請求金額、相手方の資力、証拠の状況などを踏まえた回収可能性の見通しと、必要となる弁護士費用について、丁寧に説明することを徹底しております。早期に弁護士に相談することで、交渉段階での解決が促され、結果的に訴訟を回避できるケースも多く、費用を抑えることにも繋がります。費用倒れのリスクを事前に検討し、ご納得いただいた上で手続きを進めますので、まずは一度、法律相談をご利用いただき、具体的な見通しについてお尋ねください。
解説
請負代金の未払いが発生した場合、感情的に対応するのではなく、法的な手順に沿って段階的に事を進めることが回収への近道です。ここでは、そのプロセスを3つのステップに分けて解説します。
ステップ1:交渉・催告による回収(裁判外での解決)
まずは、裁判所を利用せず、当事者間の交渉で解決を目指します。この段階で重要なのは、後の法的手続きも見据えた準備を怠らないことです。
1. 証拠の収集と整理
何よりも先に、自社の権利を裏付ける証拠を収集・整理します。これらがなければ、交渉も裁判も有利に進めることはできません。最低限、以下の書類を確認・準備してください。
- 契約関係書類
工事請負契約書、注文書・請書、見積書、仕様書、設計図書など。契約内容を特定する最も基本的な証拠です。 - 工事の履行を証明する資料
工程表、作業日報、工事写真(着工前・施工中・完成後)、引渡書、完了報告書など。契約通りに工事を完成させたことを示します。 - 追加・変更工事に関する資料
追加工事の合意書、覚書、議事録、施主の指示が記録されたメールやFAXなど。追加代金請求の根拠となります。 - 請求関係書類
請求書の控え、入金履歴がわかる預金通帳など。いつ、いくら請求し、一部でも支払いがあったかを示します。
2. 話し合いによる直接交渉
証拠を整理した上で、施主に対して未払いの理由を改めて確認し、支払いを求めます。相手が契約不適合や工期遅延を主張している場合は、その具体的な内容を聞き出し、こちらの見解を証拠に基づいて冷静に伝えます。この際、単に支払いを求めるだけでなく、相手の状況によっては支払期限の猶延や分割払いの提案など、柔軟な姿勢で臨むことが早期解決につながる場合もあります。交渉の経緯は、後の証拠とするために、日時、担当者、会話内容などを記録(議事録作成、ICレコーダーでの録音など)しておくことが望ましいです。
3. 内容証明郵便による支払催告
直接交渉での解決が難しい場合、次の手段として「内容証明郵便」を送付します。これは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
- 法的効力と効果
内容証明郵便自体に、支払いを強制する法的な力はありません。しかし、法的には「催告」にあたり、時効の完成が間近に迫っている場合に、その完成を6か月間猶予させる効果(時効の完成猶予)があります。この6か月の間に訴訟提起などの法的手続きを行う必要があります。なお、2020年4月1日以降に成立した契約の請負代金債権の消滅時効期間は、原則として権利を行使できることを知った時から5年です。 - 心理的効果
通常の郵便物とは異なり、書式や内容が厳格であるため、受け取った相手は「法的な手続きを準備している」という強い意思表示として受け止め、心理的なプレッシャーを感じます。これにより、支払いに応じるケースが少なくありません。特に、弁護士名で送付することで、その効果は一層高まります。 - 記載内容
請求金額(本体価格、消費税、遅延損害金など)、支払期限、支払方法、そして「期限内にお支払いいただけない場合は、やむを得ず法的措置を講じます」といった文言を明確に記載します。
ステップ2:裁判所の手続きを利用した回収(訴訟前段階)
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、いよいよ裁判所の手続きを利用します。しかし、当初から訴訟に進むのではなく、より簡易・迅速な手続きから検討します。
1. 支払督促
「支払督促」は、申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です 9。
- メリット
訴訟と異なり、裁判所に出頭する必要がなく、書類審査のみで手続きが進みます。申立て費用も訴訟の半額で、迅速に債務名義(強制執行を申し立てるために必要な公的文書)を得られる可能性があります。 - 流れ
支払督促を申し立て、裁判所がそれを発付します。相手方が受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、申立人は「仮執行宣言」を申し立てることができ、これにより強制執行が可能になります。 - デメリット
相手方が異議を申し立てると、自動的に通常の訴訟手続きに移行します。そのため、相手が工事内容などに明確な異議を持っており、争う姿勢が明らかな場合には不向きです。
2. 民事調停と建設工事紛争審査会
- 民事調停
「民事調停」は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が仲介役となり、当事者間の話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。手続きは非公開で行われ、訴訟のように勝ち負けを決めるのではなく、実情に即した柔軟な解決(分割払いや一部免除など)が可能です。合意が成立すると、その内容は「調停調書」に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます。 - 建設工事紛争審査会
建設工事に関する紛争に特化したADR(裁判外紛争解決手続)機関として、「建設工事紛争審査会」の利用も有効な選択肢です。この機関は、法律や建築の専門家が委員となっており、技術的な争点を含む複雑な事案において、専門的知見に基づいた解決が期待できます。ここで調停が成立した場合、その内容は民法上の「和解契約」としての効力を持ちます。単純な未払いだけでなく、工事内容の評価が争点となる場合は、専門性の高い紛争審査会の利用が戦略的に有利な場合があります。
ステップ3:訴訟・強制執行による最終的な回収
上記の手続きでも解決しない場合、最終手段として訴訟を提起し、判決を得て強制的に回収を図ります。
【債権回収手段の比較】
|
手段 |
費用 |
期間 |
相手方の同意 |
強制力 |
訴訟移行 |
|---|---|---|---|---|---|
|
内容証明郵便 |
低 |
短 |
不要 |
なし |
– |
|
支払督促 |
中 |
短 |
不要 |
高 |
異議申立てで自動移行 |
|
民事調停 |
中 |
中 |
必要 |
高(調停調書) |
不成立で終了 |
|
建設工事紛争審査会 |
中 |
中 |
必要 |
中(和解契約) |
不成立で終了 |
|
訴訟 |
高 |
長 |
不要 |
最高(判決) |
– |
1. 訴訟提起(裁判)
訴訟は、裁判所において、当事者双方が法的な主張と立証を行い、裁判官が最終的な判断(判決)を下す手続きです。
- 訴訟の流れ
原告(請負業者)が「訴状」と証拠を裁判所に提出し、被告(施主)がそれに対する反論(答弁書)を提出します。その後、複数回の「口頭弁論期日」で主張と証拠のやり取りを重ね、最終的に裁判官が判決を下します。 - 少額訴訟
請求額が60万円以下の場合は、原則1回の期日で審理を終えて判決が言い渡される「少額訴訟」という特別な手続きを利用できます。 - 勝訴のために
訴訟では、ステップ1で収集・整理した証拠が決定的に重要となります。契約の成立、工事の完成、代金額などを、客観的な証拠に基づいて論理的に主張・立証していく必要があります。
2. 強制執行(差押え)
勝訴判決を得ても相手が任意に支払わない場合、その判決(債務名義)に基づき、相手の財産を強制的に差し押さえて回収する「強制執行」を申し立てます。
- 差押えの対象相手の財産であれば、預貯金、売掛金(相手が第三者に対して持つ債権)、不動産、自動車、機械設備など、様々なものが対象となります。
- 財産調査と改正民事執行法
強制執行を成功させるには、相手がどのような財産を持っているかを把握することが不可欠です。2020年に改正された民事執行法により、「財産開示手続」が大幅に強化されました。従来、この手続は実効性が低いとされていましたが、改正により、債務者が正当な理由なく裁判所への出頭を拒んだり、虚偽の陳述をしたりした場合の罰則が、従来の「30万円以下の過料」から「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰に引き上げられました。これにより、債務者に対して財産を開示させる実効性が飛躍的に高まり、債権回収における強力な武器となっています。また、新たに「第三者からの情報取得手続」も創設され、裁判所を通じて金融機関や登記所から直接、財産情報を取得することも可能になりました。
弁護士に相談するメリット
請負代金の未払い問題は、自社で対応することも不可能ではありませんが、法的な専門知識と経験を持つ弁護士に相談・依頼することで、多くのメリットが得られます。
- 最適な回収手段の選択
弁護士は、事案の内容、証拠の有無、相手方の資力や態度などを総合的に分析し、交渉、内容証明、支払督促、調停、訴訟といった選択肢の中から、最も効果的で費用対効果の高い戦略を提案することができます。 - 交渉代理による精神的・時間的負担の軽減
施主との直接交渉は、精神的に大きなストレスがかかる上、多大な時間と労力を要します。弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、こうした負担から解放され、経営者は本業である建設事業に専念することができます。 - 法改正を反映した強力な対応
弁護士は、時効の完成猶予・更新に関する正確な法的知識に基づき対応できます。さらに、強化された財産開示手続などの最新の法制度を駆使して相手方に強力なプレッシャーをかけ、支払いを促すことが可能です。 - 法的に的確な主張・立証活動
特に訴訟になった場合、勝訴するためには、収集した証拠を法的に意味のある形で整理し、説得力のある主張を組み立てる必要があります。この専門的な作業は、法律の専門家である弁護士の得意とするところです。 - 将来のトラブル予防への貢献
弁護士は、目先の債権回収だけでなく、なぜ今回のようなトラブルが起きたのかを分析し、今後の契約書の書式見直しや、追加工事の際のルール作りなど、将来の未払いリスクを低減するための予防法務についても具体的なアドバイスを提供できます。
まとめ
建設工事の請負代金が支払われないという問題は、建設業者の経営の根幹を揺るがしかねない重大事です。しかし、決して泣き寝入りする必要はありません。
本記事で解説したように、
- ステップ1:交渉・催告
- ステップ2:訴訟前段階の裁判所手続き
- ステップ3:訴訟・強制執行
という段階的な対応を、証拠に基づいて冷静に進めていくことで、正当な権利である請負代金を回収できる可能性は十分にあります。
重要なことは、問題を先送りにせず、迅速に初動対応を開始すること、そして、どの段階であっても客観的な証拠が鍵を握るということです。もし自社での対応に限界を感じたり、法的な手続きに不安を感じたりした場合は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で建設業の実務に詳しい弁護士にご相談ください。専門家のサポートを得ることが、複雑な問題を解決し、大切な会社を守るための道筋となるはずです。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に