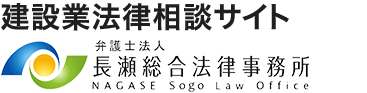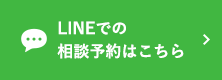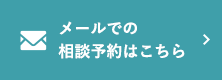2025/10/16 コラム
注文書・請書だけで契約は成立する?建設業法上の注意点とリスク
はじめに
建設業界の実務において、「注文書(発注書)」と、それに対する「請書(注文請書)」のやり取りだけで、工事の契約が交わされることは広く行われています。特に、長年にわたり取引関係が継続している相手や、比較的小規模な工事、追加工事などの場合、その都度、詳細な「工事請負契約書」を調印・作成するのは手間がかかるため、この簡便な方法が重宝されています。
しかし、この長年の慣習となっている方法には、法律上の重要な注意点や、後々の深刻なトラブルにつながりかねない重大なリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
実は、民法上は契約が成立していても、建設業界の健全な発展と発注者の保護を目的とする「建設業法」が定める要件を満たしていない場合があるのです。このギャップが、いざトラブルが発生した際に「言った、言わない」の水掛け論や、予期せぬ行政処分の原因となり得ます。
本記事では、注文書・請書による契約の法的な位置づけを明確にするとともに、そこに潜む建設業法上の注意点と具体的なリスク、そしてそれらのリスクを回避するための、実務的かつ望ましい契約方法について、弁護士が解説します。
Q&A
Q1: いつも取引している元請業者とは、元請から送られてくる注文書に社印を押して請書として返送するだけで工事をしています。これだけで、法的に契約は成立しているのでしょうか?
はい、民法上は、契約は有効に成立しています。民法では、契約は当事者間の「申込み」と「承諾」という意思表示が合致すれば成立するのが原則です。このケースでは、元請業者が発行する注文書が契約の「申込み」にあたり、貴社が返送する請書がその申込みに対する「承諾」にあたります。したがって、当事者間の権利義務関係(工事を完成させる義務や代金を支払う義務)は、法的に有効なものとなります。
問題は、その契約の「内容」が、建設業法が求める基準を満たしているかどうか、という点にあります。民法上有効な契約であっても、建設業法に違反している可能性があり、それがリスクとなります。
Q2: 建設業法では、契約書に記載すべき事項が定められていると聞きました。一般的な注文書と請書だけでは、具体的に何が問題になるのですか?
ご指摘の通り、建設業法第19条第1項では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して最低限16の事項を記載した書面を交付しなければならないと定めています。
一般的な注文書・請書の書式では、工事内容、請負代金額、工期、支払方法といった基本的な項目は記載されています。しかし、法律が要求する事項の中には、例えば以下のような、トラブルが発生した際のルールに関する項目が含まれています。
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担(例:台風で現場が被害を受けた場合の対応)
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法(例:どの裁判所で裁判をするかなど)
これらの記載が漏れていると、建設業法違反となり、監督処分の対象となる可能性があります。
Q3: 注文書に記載のない事項で、施主とトラブルになりました。例えば、予期せぬ地中障害物が出てきた際の追加費用の負担についてです。契約書がない場合、どのように解決すればよいのでしょうか?
注文書・請書に記載のない事項については、当事者間に明確な合意がなかったということになり、原則として民法や関連法規の定めに従って解決されることになります。しかし、その法律の解釈をめぐって双方の主張が対立し、紛争が長期化・複雑化するリスクが高まります。
ご質問のケースでは、地中障害物の除去費用をどちらが負担するかについて、民法の危険負担の原則などを元に争うことになりますが、明確な合意がないため、交渉は難航し、最終的には裁判で判断を仰ぐしかなくなる可能性が高いでしょう。このような事態を防ぐためにも、事前にリスクを想定し、必要な事項を書面で合意しておくことが重要なのです。
解説
注文書・請書による契約は、手軽で便利な反面、その手軽さが仇となって大きなトラブルを招くことがあります。その法的構造とリスクを正しく理解し、適切な対策を講じましょう。
1. 注文書・請書による契約の「二重構造」
注文書・請書による契約は、「民法」と「建設業法」という二つの法律の観点から見る必要があります。
- 民法上の契約成立: 前述の通り、民法では、契約は口約束でも成立する「不要式契約」が原則です。書面は、合意内容を証拠として残すためのものに過ぎません。発注者からの「注文書(申込み)」に対し、受注者が「請書(承諾)」を交付した時点で、両者の意思は合致し、工事請負契約は法的に有効に成立します。
- 建設業法上の要請: 一方で、建設業界の特殊性(高額な取引、専門性の高さ、トラブルの多さ)に鑑み、建設業法は、民法の原則に特別なルールを上乗せしています。それが建設業法第19条です。この条文は、建設工事の請負契約の適正化を図るため、当事者に対して、後述する法定の16事項を記載した書面を作成し、署名または記名押印して相互に交付することを義務付けています。これは、口約束や曖昧な取り決めによる「言った、言わない」のトラブルを未然に防止するための、行政法規上の重要なルールです。
つまり、「民法上は有効だが、建設業法上は違反」という状態があり得る、ということを理解する必要があります。
2. 建設業法が求める16の法定記載事項
建設業法第19条第1項および同施行令第6条で定められている、契約書面に記載すべき16の事項は以下の通りです。これらが自社の注文書・請書に網羅されているか、確認してみてください。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
3. 注文書・請書だけに頼る具体的なリスク
一般的な注文書・請書のフォーマットでは、上記のリストのうち、特に5番以降の「もしも」の事態、つまりトラブル発生時や将来の不確定要素に関する取り決めが記載されていないことがほとんどです。この記載漏れが、以下のような具体的なリスクを生み出します。
建設業法違反によるリスク(コンプライアンスリスク)
法定記載事項を欠いた書面しか交付していない場合、それは明確な建設業法違反です。これが発覚した場合、国土交通大臣や都道府県知事から指示処分や、悪質な場合には営業停止処分といった重い監督処分を受ける可能性があります。公共工事の指名停止につながることもあり、企業の信用に関わる重大なリスクです。
トラブル発生時のリスク(紛争リスク)
-
- 仕様変更: 施主からの「ちょっとした仕様変更」があった際に、代金や工期をどう見直すかのルールがないため、「サービスでやってくれると思った」「こんなに高くなるとは思わなかった」といった紛争に発展します。
- 不可抗力: 記録的な豪雨や大地震で資材が損傷したり、工期が遅れたりした場合の損害負担や工期延長のルールが不明確なため、責任の押し付け合いになります。
- 契約不適合(瑕疵): 完成後に雨漏りなどの不具合が見つかった場合、どのような期間、どのような方法で保証するのかが曖昧なため、施主から過大な要求を受けたり、対応をめぐって延々と争いになったりします。
- 紛争解決: トラブルが裁判になった場合、どこの裁判所で裁判をするか(管轄)の定めがないと、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所になります。遠方の顧客とのトラブルでは、裁判のために毎回多大な時間と費用をかけて遠征しなければならない、という不利益を被る可能性があります。
4. リスクを回避するための、実務的で望ましい契約方法
では、どうすればよいのでしょうか。毎回、16事項を網羅した分厚い契約書を作成するのは非効率です。そこで、注文書・請書の手軽さを活かしつつ、建設業法を遵守し、将来のトラブルを予防するための有効な方法が、「基本契約書」と「個別契約(注文書・請書)」を組み合わせる方法です。
- ステップ1:基本契約書の締結
継続的に取引がある相手方とは、まず最初に、取引全般に共通する基本的なルールを定めた「工事請負基本契約書」を一度だけ締結します。この基本契約書に、上記で挙げた法定記載事項のうち、個別の工事内容に依らない共通事項(損害の負担、契約不適合責任、紛争解決方法、違約金など、主に5番以降の項目)を網羅しておきます。 - ステップ2:個別契約の締結
その後、個別の工事を発注する際には、工事内容、代金額、工期など、その工事に固有の事項のみを記載した注文書・請書を取り交わします。この注文書・請書には、「本件工事の契約条件は、別途締結済みの〇年〇月〇日付工事請負基本契約書の定めに従うものとする」といった一文(参照条項)を入れておくことが重要です。
この二段階の契約方式であれば、毎回詳細な契約書を作成する手間を省きつつ、全体として法定記載事項を網羅した契約関係を構築することができます。
弁護士に相談する具体的なメリット
自社に合った契約書式の作成
弁護士に依頼すれば、貴社の事業内容(新築、リフォーム、専門工事など)や取引の実態に合わせて、建設業法に準拠し、かつ将来のリスクを最大限にヘッジできる「工事請負基本契約書」や、注文書・請書の雛形をオーダーメイドで作成することができます。
既存書式のリーガルチェック
現在使用している注文書・請書の書式に、法的な問題点や自社に不利な条項が含まれていないかを専門家の視点でチェックし、具体的な改善点をアドバイスします。
トラブル発生時の的確な対応
契約内容が不十分なままトラブルが発生してしまった場合でも、民法や建設業法の原則に立ち返り、貴社の権利を最大限に主張するための法的な戦略を立て、代理人として交渉にあたることが可能です。
まとめ
注文書と請書のやり取りだけで、民法上の契約は成立しますが、それだけでは建設業法が求める要件を満たさず、「コンプライアンス違反」と「将来の紛争」という二つの大きな法的リスクを抱え込むことになります。「今まで問題なかったから大丈夫」という考えは、いつ重大なトラブルに発展してもおかしくない、危険な状態です。
将来の予期せぬトラブルから会社を守り、健全な事業運営を継続するためには、契約の基本に立ち返り、法定記載事項を網羅した書面を取り交わすことが重要です。
継続的な取引先とは「基本契約書」を締結し、個別の工事は「参照条項付きの注文書・請書」で行うという二段階の契約方式は、コンプライアンスと業務効率を両立させるための、現代の建設業者にとっての有効な対策と言えるでしょう。自社の契約方法に少しでも不安がある場合は、ぜひ一度、企業法務を扱う弁護士にご相談ください。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に