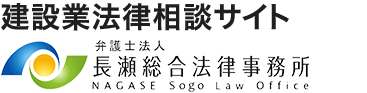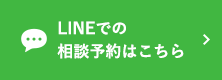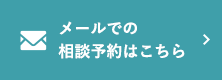2025/10/14 コラム
工事代金の未払いで「工事ストップ」は可能か?法的リスクと注意点
はじめに
建設工事は、その性質上、工期が数ヶ月から数年に及ぶことが少なくありません。そのため、契約内容に応じて、着手金、中間金、あるいは出来高払いといった形で、工事の進捗に合わせて代金が分割で支払われるのが一般的です。これらは建設会社の資金繰りを支え、工事を円滑に進めるための生命線ともいえる重要な支払いです。
しかし、この重要な中間金などが、約束の期日通りに施主(注文者)から支払われない、という事態は残念ながら頻繁に発生します。このような状況に陥った建設業者の皆様が、「支払いがなされるまで、工事を止めてしまいたい」と考えるのは、経営判断として、また感情的にももっともなことでしょう。
工事を一時的に中断(ストップ)することは、施主に対して支払いを促すための対抗手段となり得ます。しかし、その一方で、この「工事ストップ」という手段の行使は、法的なリスクも伴います。もし、その行使が法的に正当と認められなければ、状況は一変します。請負業者側が工期遅延の責任を問われ、施主から多額の損害賠償を請求されるという、まさに本末転倒の深刻な事態に発展しかねません。
本記事では、施主による工事代金の未払いを理由とした工事ストップが、どのような場合に法的に可能なのか、その法的根拠は何か、そして、その強力な手段を行使する際に伴う重大なリスクと、実行前に必ず確認・実行すべき注意点について解説します。
Q&A
Q1: 施主から契約で定められた中間金が支払われません。このまま工事を続けても、最終的に全額支払われるのか非常に不安です。今すぐにでも工事を止めても法的に問題ないでしょうか?
いいえ、「すぐに」無条件で工事を止めるのは大変危険です。工事ストップが法的に正当な権利行使として認められるためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
まず第一歩は、工事請負契約書の内容を再確認することです。支払いの期日や条件がどのように定められているかを確認し、相手方の契約違反が明確であることを確認します。その上で、支払いが遅れている事実を客観的に指摘し、「相当の期間」を定めて支払いを催告することが必要です。この催告は、後に法的な紛争になった際の重要な証拠となるため、内容証明郵便を利用して書面で行うべきです。
この催告をしてもなお施主が支払いに応じない、という状況になって初めて、工事ストップの正当性が認められる可能性が出てきます。感情的になって突然に工事を中断してしまうと、それは請負業者側の一方的な契約違反(履行遅滞)と見なされ、施主から工期遅延に伴う損害賠償を請求されるという深刻なリスクを負うことになります。
Q2: 工事を一時的に中断する旨を内容証明郵便で通知したところ、施主の代理人弁護士から「契約違反だ。工期が遅れた分の損害を賠償してもらう」という反論が書面で届きました。どう対応すればよいですか?
このような状況では、冷静な対応が求められます。最も重要なのは、こちらの工事ストップが法的に正当な権利の行使であることを、根拠をもって反論することです。
そのためには、以下の事実を客観的な証拠(契約書、請求書、内容証明郵便など)に基づいて整理し、法的な主張を組み立てる必要があります。
- 契約書上の支払義務の存在:契約書のどの条項に基づいて、いつ、いくらの支払義務があるのか。
- 支払いが遅延している事実:期日を過ぎても入金がないことを示す通帳のコピーや経理記録。
- こちらが支払いを正式に催告した事実:送付した内容証明郵便とその配達証明書。
相手方も弁護士を立ててきた以上、これ以上の直接交渉は感情的な対立を深めるだけで得策ではありません。相手の主張が法的に妥当なものか、こちらの対抗措置にリスクはないかを冷静に判断するためにも、このような状況になった場合は、弁護士にご相談ください。専門家として、相手方への法的な反論の組み立てをサポートし、交渉の代理人として冷静な解決を目指します。
Q3: 私は専門工事を行う下請業者ですが、元請業者からの支払いが2ヶ月以上滞っています。工事を止めたいのですが、施主や他の専門工事業者に迷惑がかかるのが心配ですし、元請との関係が悪化するのも避けたいです。どうすべきでしょうか?
下請業者の立場での工事ストップは、元請業者との間の契約関係だけでなく、工事全体の工程に大きな影響を与え、施主や他の関係業者にも多大な迷惑をかける可能性があるため、より慎重な判断が求められます。
安易に工事を止めると、元請から工期遅延による損害賠償を請求されるだけでなく、現場全体の混乱を招き、建設業界内での信用を失ってしまうという、事業の存続に関わるリスクもはらんでいます。
まずは、工事ストップという手段の前に、取りうる他の選択肢を検討すべきです。
- 元請への催告: 内容証明郵便を送付し、支払いを強く求めます。これにより、元請に事の重大さを認識させ、支払いを促す効果が期待できます。
- 上位の注文者への働きかけ: 建設業法には、下請負人が元請負人に対して有する請負代金債権について、特定建設業者である元請負人が発注者に対して有する請負代金債権(出来高払い等)から、その下請負人が支払いを受けられるように配慮を求める規定があります。これに基づき、発注者(施主)に対して状況を説明し、協力を求めることも考えられます。
- 工事ストップ以外の債権回収手段: 工事は継続しつつ、元請の資産(銀行口座や売掛金など)を仮差押えするなどの法的手続きを検討します。これにより、工事への影響を最小限に抑えながら、債権の保全を図ることが可能です。
どの手段がリスクが低く効果的かは、契約内容や元請の経営状況によって異なります。専門家である弁護士に相談し、包括的な視点から最適な戦略を練ることをお勧めします。
解説
代金が支払われないからといって、感情的に工事をストップすることは法的リスクを伴います。その行為が正当化されるためには、法律上の明確な根拠が必要です。ここでは、その根拠となる権利、そして安易な工事ストップに伴うリスクについて解説します。
1. 工事ストップを検討する際の法的根拠
請負業者が代金未払いを理由に工事を中断する際の主な法的根拠は、民法に定められた「同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)」です。
同時履行の抗弁権(民法第533条)とは
請負契約のように、当事者双方が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約(双務契約)において、相手方がその債務を履行するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるという、公平の原則に基づいた権利です。
これを建設工事請負契約に当てはめてみましょう。
- 請負業者: 工事を完成させる債務
- 注文者(施主): 請負代金を支払う債務
この二つの債務は、互いに対価関係にあります。特に、契約書で「第〇工程が完了した時点で中間金〇〇円を支払う」と明確に定められている場合、その「中間金の支払い」と「次工程以降の工事の続行」は、密接な牽連(けんれん)関係にあると考えられます。
したがって、施主が正当な理由なく中間金の支払いを怠った場合、請負業者は「中間金が支払われるまで、次の工程の工事は行いません」と主張し、工事を中断することが、この同時履行の抗弁権の行使として正当化される可能性があります。
契約書上の「工事中断権」の条項
より明確な根拠として、工事請負契約書や、国土交通省が作成した「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」などには、注文者の代金不払いを理由とする請負業者の工事中断権が明記されている場合があります。例えば、「注文者が正当な理由なく請負代金の支払いを遅滞したときは、請負業者は工事を中断することができる」といった趣旨の条項です。このような特約があれば、工事ストップの正当性は明確になります。契約締結時に、このような条項が含まれているかを確認しておくことが、将来のリスク管理において非常に重要です。
2. 安易な工事ストップに伴う重大な法的リスク
もし、上記の法的根拠が認められない状況、例えば、催告が不十分であったり、相手の支払遅延に正当な理由(例:工事に重大な欠陥があるなど)があったりする場合に工事をストップしてしまうと、それは請負業者側の一方的な「債務不履行」となり、以下のような深刻なリスクを負うことになります。
工期遅延による損害賠償責任
工事ストップが不当と判断された場合、その中断期間はすべて請負業者の責任による工期の遅延となります。その結果、施主が被った損害について、賠償責任を負うことになります。具体的には、以下のような損害が想定されます。
-
- 店舗や工場の場合: オープンの遅延による逸失利益(本来得られたはずの売上)
- 賃貸物件の場合: 入居開始の遅延による逸失賃料
- 住宅の場合: 完成までの仮住まい費用の追加負担分
- 遅延損害金: 契約書に定められた利率に基づく遅延損害金
未払い代金を回収しようとした結果、それをはるかに上回る金額の賠償金を支払うという事態になりかねません。
施主(注文者)による契約解除
請負業者の不当な工事ストップは、民法上の「履行遅滞」に該当し、施主側から契約を解除する正当な理由を与えてしまうことになります。契約が解除されると、当然ながらそれ以降の工事を行うことはできなくなり、将来得られるはずだった工事の利益をすべて失います。さらに、解除に伴い施主に生じた損害(例:別の業者に引き継ぎを依頼するための追加費用など)についても、賠償を請求される可能性があります。
信頼関係の喪失と信用の失墜
法的なリスクはもちろんですが、一度工事をストップすると、施主との信頼関係は修復不可能なほど損なわれます。また、その情報が業界内で広まれば、「代金トラブルで現場を止める業者」というネガティブな評判が立ち、金融機関からの評価や今後の受注活動に長期的な悪影響が及ぶ可能性も否定できません。
3. 工事をストップする前に確認・実行すべきこと
上記のリスクを回避し、正当な権利として工事ストップを行うためには、感情に流されることなく、以下のステップを慎重に、かつ確実に踏む必要があります。
1 契約書の徹底的な再確認
まずは、原点である工事請負契約書を隅々まで確認します。
- 支払条件: 中間金などの支払時期、金額、支払方法がどのように定められているか。支払いの前提条件(例:特定の工程の完了、検査の合格など)はないか。
- 工事中断に関する条項: 代金不払いの場合に工事を中断できる旨の特約があるか。その場合の手続き(事前の通知義務など)が定められていないか。
- 遅延損害金に関する条項: 施主の支払いが遅れた場合の利率はどうなっているか。
- 紛争解決条項: トラブルになった際の管轄裁判所はどこか。
2 書面による履行の催告(内容証明郵便の活用)
いきなり工事を止めるのではなく、必ず事前に書面で支払いを催告します。この際、普通郵便やメールではなく、「内容証明郵便」に「配達証明」を付けて利用するのが有効です。
記載内容のポイント
- 契約書第〇条に基づき、〇月〇日期日の未払金〇〇円の支払い義務があること。
- 本書面到着後、〇日以内(例:7日~10日程度)に指定口座へ支払うよう要求すること。
- 「万一、上記期限内にお支払いいただけない場合は、誠に不本意ながら、民法第533条(または契約書第〇条)に基づき、工事を中断せざるを得ませんので、ご承知おきください」といった、工事中断を予告する文言を明確に記載すること。
法的証拠としての価値
内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の文書を相手方に送ったかを郵便局が公的に証明してくれるため、後に裁判などになった際に、こちらが正式に催告を行い、相手に支払いの機会を与えたことを証明する証拠となります。
3 専門家(弁護士)への早期相談
工事ストップは、その判断に高度な法的知識を要する重大な経営判断です。上記のステップと並行して、あるいは催告しても支払いがない時点で、弁護士に相談してください。弁護士は、契約内容や現在の状況を客観的に分析し、工事ストップに踏み切ることが法的に正当かどうか、他に取るべき手段はないか(仮差押えなど)、そして実行した場合の潜在的リスクは何かを的確にアドバイスします。
弁護士に相談する具体的なメリット
代金未払いに伴う工事ストップの検討という重大な局面において、弁護士は以下のような具体的なサポートを提供できます。
- 法的リスクの的確な分析と判断
契約書やこれまでの経緯、証拠関係を精査し、ご状況で工事ストップが可能か、また、それに伴うリスクはどの程度かを専門家の見地から冷静に分析・判断します。感情論や憶測を排し、法的な見通しを明確に示します。 - 効果的な催告書の作成と送付
単に支払いを求めるだけでなく、法的要件を満たし、かつ相手方に支払いを促す効果が最も高い内容証明郵便の文面を作成します。弁護士名で送付することで、「これは単なる請求ではなく、法的措置への最終通告である」という心理的プレッシャーを与え、支払いを実現する可能性を高めます。 - 施主との交渉代理
弁護士が代理人として施主やその代理人弁護士と交渉することで、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いが可能になります。支払いの確約を取り付けたり、分割払いの合意形成を図ったりと、紛争の拡大を防ぎ、円満な解決策を模索します。 - 代替手段の提案と実行
仮に、工事ストップのリスクが高いと判断した場合には、闇雲に実行するのではなく、工事は継続しつつ、未払代金の回収を図るための別の法的手段(預金や不動産の仮差押え、支払督促、訴訟など)を迅速に提案し、実行に移すことができます。
まとめ
工事代金の未払いを理由とした「工事ストップ」は、請負業者に残された強力な対抗手段の一つであり、正当な権利です。しかし、それは諸刃の剣であり、その行使には法的な正当性が厳格に求められることを決して忘れてはなりません。
安易な判断で工事を中断すれば、未払金回収どころか、多額の損害賠償責任を負うという最悪の結果を招きかねません。このような事態を絶対に避けるため、工事ストップという最終手段を検討する際には、
- 契約書を再確認する
- 内容証明郵便で明確に催告する
- 実行前に弁護士に相談する
という手順を守ってください。専門家である弁護士の助言を得ながら、慎重かつ戦略的に対応することが、最終的に貴社の正当な権利とキャッシュフロー、そして信用を守るための道筋となります。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に