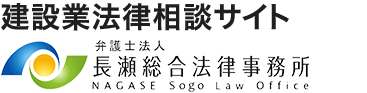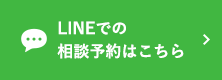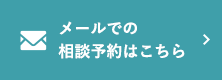2025/10/13 コラム
口約束で進めた工事の代金は請求できるか?法的な考え方と対処法
はじめに
建設業界では、工期の切迫や長年の取引関係から、「契約書を交わすまでもない」として、口約束だけで工事が進められてしまうことが、今なお少なくありません。しかし、工事完了後、いざ代金を請求する段になって「そんな約束はしていない」「金額が高すぎる」などと言われ、代金が支払われないというトラブルは絶えません。
書面がない以上、もう請求はできないのだろうか、と諦めてしまう経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法的には、たとえ口約束であっても、代金を請求する道は閉ざされているわけではありません。
本記事では、契約書が存在しない、口約束のみで進めた工事について、代金を請求するための法的な考え方と、そのために必要となる具体的な対処法、そして集めるべき証拠について解説します。
Q&A
Q1: 施主との間で、契約書や注文書といった書類が一切存在しません。それでも、行った工事の代金を請求することは法的に可能ですか?
はい、可能です。日本の民法では、契約は当事者双方の意思表示が合致すれば、書面がなくても口頭で有効に成立します(これを「諾成契約」といいます)。したがって、口約束であっても「工事を行う」という申込みと、「お願いします」という承諾があれば、法的には有効な請負契約が成立しており、請負業者には代金を請求する権利が発生します。一方で、建設業法第19条は契約書面の交付を義務付けており、これに違反すると行政処分の対象となる可能性があります。しかし、判例上、この建設業法の規定は行政上の「取締法規」と解されており、これに違反したからといって、当事者間の契約の私法上の効力(契約の有効性)そのものが直ちに否定されるわけではありません。
Q2: 口約束の存在を証明するには、どのようなものが証拠になるのでしょうか?
口約束の契約を証明するためには、「契約があったこと」を推認させる間接的な証拠(状況証拠)を積み重ねることが重要になります。具体的には、 ① 施主との間でやり取りしたメールやFAX、 ② 工事の見積書や請求書(相手に送付したもの)、 ③ 工事の施工前・中・後の写真、 ④ 作業日報、 ⑤ 資材の発注書や納品書、 ⑥ 工事の事実を知っている従業員や協力業者の証言、 ⑦ 会話の録音データなどが有効な証拠となり得ます。
Q3: 相手は工事を依頼したこと自体は認めていますが、「そんな高額な代金になるとは聞いていない」と言って、支払いに応じてくれません。どうすればよいですか?
代金額について明確な合意があったことを証明できない場合でも、代金請求権がなくなるわけではありません。このようなケースでは、裁判になった場合、裁判所は「相当な報酬額」を認める傾向にあります。したがって、請求する側としては、その工事に要した材料費、労務費、諸経費などを詳細に積み上げた積算書を作成し、さらに同業他社の同種工事における一般的な料金体系などを示すことで、請求額が社会通念上「相当」であることを合理的に主張・立証していくことになります。
解説
口約束による工事代金請求の最大の課題は、契約書という直接的な証拠がない中で、いかにして「契約の存在」と「その内容」を裁判官などの第三者に納得してもらうか、という点に尽きます。
口約束でも契約は成立するが、問題は「立証責任」
前述の通り、民法上、契約の成立に書面は必須ではありません。口頭での合意があれば、請負契約は有効に成立します(諾成契約)。
しかし、建設業法第19条は、建設工事の請負契約の当事者に対し、契約内容を記載した書面の作成・交付を義務付けています。この規定に違反すると、監督処分の対象となる可能性はありますが、それをもって直ちに当事者間の契約が無効になるわけではありません。裁判例は、建設業法第19条を、行政上の目的から事業者に一定の義務を課す「取締法規」であると解しています。そのため、この規定に違反しても、契約の私法上の効力(当事者間の権利義務関係)は有効であると判断されています。
したがって、法的な問題は「契約が無効であること」ではなく、相手方が「そんな約束はしていない」と契約の存在自体を否定した場合に、契約の存在を証明する責任(立証責任)が、代金を請求する側、すなわち請負業者側にあるという点です。請求する側が、客観的な証拠をもって裁判所を説得できなければ、権利はあっても請求は認められません。
口約束の契約内容を証明するための「証拠」をかき集める
契約書がない以上、あらゆる間接的な証拠を収集し、それらを組み合わせることで、契約の存在と内容を浮かび上がらせる必要があります。以下のようなものが証拠となり得ます。
- 書類関係
- 見積書・請求書: 相手方に交付したものであれば、契約内容(特に金額)を示す有力な証拠です。
- 銀行の振込履歴: もし一部でも代金が支払われている場合、契約の存在を強く推認させます。
- 手書きのメモや図面: 打ち合わせ時に作成したもので、相手の押印やサインがなくても、状況証拠の一つとなります。
- 電子データ
- メール・FAX・ビジネスチャット: 「〇〇の件、進めてください」「〇〇の色はAでお願いします」といった、工事の依頼や仕様に関するやり取りが残っていれば、極めて重要な証拠です。
- ウェブサイトの問い合わせフォームの履歴: 最初のコンタクトがウェブ経由であれば、その記録も証拠になります。
- 現場の記録
- 工事写真: 施工前・施工中・施工後の写真は、工事の事実と内容を証明する客観的な証拠です。施主が現場で立ち会っている様子が写っていれば、なお良いでしょう。
- 作業日報: 日々の作業内容、作業員、使用した資機材などが記録されていれば、工事の実行を裏付けます。
- 資材の納品書・領収書: その工事のために特別に仕入れた資材があれば、工事の存在を間接的に証明します。
- 人の証言・会話の記録
- 第三者の証言: 下請業者や設計担当者、自社の従業員など、施主とのやり取りを見聞きしていた人の証言も証拠となります。
- 会話の録音: 相手の同意を得ていない録音であっても、違法な手段で録音されたものでない限り、裁判で証拠として認められる可能性は高いです。ただし、使い方には注意が必要です。
請求を実現するための具体的な対処ステップ
Step1: 証拠の収集と整理
まずは、上記で挙げたような証拠を可能な限りかき集め、時系列に沿って整理します。何が契約の成立を裏付け、何が工事の内容や金額を裏付けるのかを分類しておきましょう。
Step2: 請求書と内容証明郵便の送付
収集した証拠を基に、工事内容と請求金額の内訳を明記した請求書を作成し、相手方に送付します。通常の郵便で反応がない場合は、「内容証明郵便」を利用して、支払いを催告します。その際、「本書面到着後、〇日以内にお支払いなき場合は、やむを得ず法的措置に移行します」といった文言を加え、こちらの強い意思を示します。この催告には、時効の完成を6か月間猶予させる効果があります。
Step3: 弁護士を通じた交渉
当事者間での話し合いが難しい場合は、弁護士に交渉を依頼することを検討します。弁護士が代理人として介入することで、相手方も事態を真剣に受け止め、支払いに応じる可能性が高まります。また、弁護士は収集した証拠の法的な価値を評価し、説得力のある交渉を行うことができます。
Step4: 法的手続き(支払督促・調停・訴訟)
交渉が決裂した場合は、支払督促、民事調停、あるいは訴訟といった裁判所の手続きを利用します。訴訟では、収集した証拠を提出し、証人尋問などを行いながら、裁判官に契約の成立と代金額の妥当性を認定してもらうことになります。
弁護士に相談するメリット
口約束のトラブルは、証拠が乏しく、法的な主張の組み立てが複雑になりがちです。このような状況でこそ、弁護士に相談するメリットは大きいと言えます。
- 証拠の評価と収集の助言: 手元にある断片的な情報や資料の中から、法的に有効な証拠となり得るものを見つけ出し、その証明力を評価します。また、弁護士会照会制度など、弁護士にしかできない方法で、さらなる証拠を収集することも可能です。
- 論理的な主張の構築: 集めた証拠を効果的に組み合わせ、契約が有効に成立し、請求額が妥当であることを、法的に筋道の通った形で主張することができます。特に、建設業法違反と契約の有効性に関する「取締法規」の論点などを的確に主張し、相手方の誤った反論を排斥します。
- 相手方との交渉代理: 感情的な対立に陥りがちな当事者間の交渉を、弁護士が冷静かつ戦略的に進めます。これにより、訴訟に至る前に、交渉段階での解決を図れる可能性も高まります。
- 訴訟手続きの遂行: 万一、訴訟になった場合でも、複雑な手続きや書面作成、法廷での弁論活動など、専門家として全てを代理し、依頼者の利益を最大限に守るために尽力します。
まとめ
口約束で進めた工事の代金も、法的には請求可能です。決して諦める必要はありません。
しかし、その請求が認められるかどうかは、ひとえに「契約の存在と内容を、客観的な証拠でいかに証明できるか」にかかっています。
今回のトラブルを教訓とし、今後はどんなに些細な工事でも必ず書面を交わすことを徹底するとともに、万一の場合に備えて、日頃からメールでのやり取りや現場写真、作業日報といった記録を意識的に残す習慣をつけることが、貴社の経営を守る上で不可欠です。
すでに口約束による未払いトラブルでお困りの場合は、証拠が散逸してしまう前に、できるだけ早く建設業界の法務に詳しい弁護士にご相談ください。解決への道筋を、専門家が具体的に示します。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に