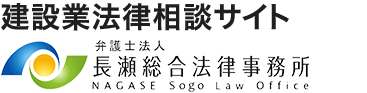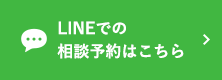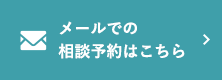2025/10/11 コラム
追加・変更工事の代金請求で失敗しないための注意点と証拠の残し方
はじめに
建設工事の現場では、当初の計画にはなかった工事が、施主の要望や現場の状況に応じて発生することが日常茶飯事です。こうした「追加・変更工事」は、建設業者にとって売上を確保する機会であると同時に、代金未払いという大きなトラブルの原因にもなり得ます。
「良かれと思ってサービスで対応したのに、代金が支払われない」「口頭で頼まれた工事なのに、後から『頼んでいない』と言われた」――。このような悔しい経験をされた建設業者の皆様も多いのではないでしょうか。追加・変更工事の代金請求をめぐるトラブルの多くは、事前の取り決めが曖昧なまま工事を進めてしまうことに起因します。
本記事では、このようなトラブルを未然に防ぎ、行った仕事に見合う代金を確実に請求するために、建設業者が押さえるべき法的な注意点と、万一の紛争に備えるための具体的な証拠の残し方について解説します。
Q&A
Q1: 現場で施主から「ついでにここも直してほしい」と口頭で指示され、対応しました。しかし、請求段階になって「そんなことは頼んでいない」と支払いを拒否されています。もう請求は不可能でしょうか?
諦めるのはまだ早いです。法的には、口頭の合意でも契約は成立します。問題は、その「合意があったこと」を証明できるか否かです。例えば、施主の指示を聞いていた他の職人の証言、追加工事部分の施工中・施工後の写真、関連する資材の発注書、作業日報の記録など、状況証拠を積み重ねることで、合意の存在を立証できる可能性があります。しかし、証明のハードルは高くなるため、今後は必ず書面での確認を徹底することが重要です。
Q2: 追加工事の金額について、事前に明確な合意がありませんでした。「よしなに頼む」と言われて進めたのですが、請求額に納得してもらえません。どのように金額を算定すればよいですか?
金額の合意がない場合でも、工事の実施について合意があったのであれば、代金を請求する権利はあります。この場合、請求できるのは「相当な報酬額」となります。具体的には、その工事にかかった材料費、労務費、経費などを積み上げた上で、同種の工事の一般的な市場価格や、貴社の標準的な見積単価など、客観的な根拠に基づいて合理的な金額を算出し、相手方に丁寧に説明する必要があります。見積書を事後的に作成し、その内訳を明確に示すことが交渉の第一歩となります。
Q3: 元請業者から「施主から言われたから、とりあえずこの作業やっておいて」と指示されました。書面はありませんが、下請代金として請求できますか?
請求は可能です。しかし、元請業者との間でも「言った言わない」のトラブルになりがちです。下請業者の立場としては、元請からの指示であっても、できる限りメールやFAX、ビジネスチャットなど、記録に残る形で指示内容の確認を求めるべきです。また、建設業法では、元請負人は下請負人に対し、契約内容を記載した書面を交付する義務があります(建設業法第19条)。さらに、元請と下請の資本金規模によっては「下請法」が適用される場合があります。下請法が適用される場合、親事業者(元請)には、発注内容を記載した書面(3条書面)を直ちに交付する、より厳格な義務が課せられています(下請法第3条)。この規定を根拠に、元請に対して書面の交付を求めることも、自社の身を守る上で重要です。
解説
追加・変更工事の代金請求で失敗しないためには、「なぜトラブルが起きるのか」を理解し、その原因を一つずつ潰していく地道な作業が不可欠です。
なぜ追加・変更工事でトラブルが起きるのか?
- 安易な口約束: 現場の勢いや人間関係を優先し、書面を取り交わさずに工事を開始してしまう。
- 認識の齟齬: 工事の範囲、仕様、金額、工期について、当事者間の認識がずれている。
- 証拠の不存在: 工事が完了してから「言った言わない」の水掛け論になり、合意内容を証明する客観的な証拠がない。
- 法律への理解不足: 建設業法や下請法が定める書面交付義務などを遵守していない。
これらの原因を踏まえ、代金請求を成功させるために実践すべき具体的な注意点と、証拠の残し方を解説します。
代金請求を成功させるための5つの注意点
1. 「着工前の書面合意」を鉄則とする
最も重要かつ基本的な原則です。どんなに小規模な追加・変更工事であっても、必ず工事に着手する前に、書面で合意を取り交わすことを徹底してください。これは、建設業法第19条で定められた、契約書面の交付義務を遵守する上でも不可欠です。特に、同条2項は、当初の契約内容を変更する場合にも、変更内容を記載した書面を相互に交付することを明確に義務付けています。
最低限、以下の事項を記載した「追加工事合意書」や「変更契約書」を作成しましょう。
- 追加・変更する工事の具体的な内容
- 数量、単価、金額(消費税の扱いも明確に)
- 変更後の請負代金総額
- 変更後の工期
- 追加代金の支払条件
- 両当事者の署名・捺印
2. 見積書を必ず提示し、承諾を得る
金額に関する認識の齟齬を防ぐため、追加・変更工事の見積書を必ず作成し、事前に相手方に提示して承諾を得てください。口頭での承諾だけでなく、見積書に署名・捺印をもらうのが最も確実です。それが難しい場合でも、メールやビジネスチャットで「この見積内容で進めてください」といった返信をもらっておくだけで、有力な証拠となります。
3. 工事内容・範囲を明確に記録する
当初の契約に含まれる工事範囲と、追加・変更工事の範囲を、図面や仕様書上で明確に区別できるように記録を残しましょう。例えば、変更前の図面と変更後の図面を両方保管する、変更箇所を色分けして示すなどの工夫が有効です。これにより、「それは当初の契約に含まれているはずだ」といった主張を防ぐことができます。
4. 日々の作業報告(日報)を具体的に記録する
作業日報は、日々の業務記録であると同時に、万一の際の重要な証拠となります。特に、追加・変更工事を行った日には、「誰の指示で」「どのような追加作業を」「どれくらいの時間(人数)で」行ったのかを具体的に記載しておきましょう。この日々の記録の積み重ねが、口約束しか存在しない場合の請求の根拠を補強してくれます。
5. 元請・下請間では下請法の遵守を意識する
下請業者として工事を行う場合は、特に注意が必要です。建設業法は全ての建設工事請負契約に適用されますが、元請と下請の資本金規模によっては、下請業者をより強力に保護する「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が適用されます。下請法が適用される取引では、親事業者(元請)は、下請事業者(下請)に追加工事を依頼した場合、その内容等を記載した書面(通称「3条書面」)を直ちに交付する義務があります(下請法第3条)。また、親事業者が一方的に低い金額を定めたり(買いたたき)、正当な理由なく代金を減額したりすることは、下請法で厳しく禁止されています。これらの法律知識を念頭に置き、不当な扱いを受けないよう、元請とのやり取りは慎重に行いましょう。
万一の紛争に備える!有効な証拠の残し方
いかに注意していても、トラブルが起きてしまう可能性はゼロではありません。その際に自社を守ってくれるのが、客観的な「証拠」です。以下のものを意識的に残し、整理・保管しておきましょう。
- 書面
- 追加工事合意書、変更契約書、覚書
- 見積書、注文書、請書
- 打ち合わせの議事録(双方の署名があればより強力)
- 電子データ
- メールの送受信履歴(合意内容や指示が記載されたもの)
- ビジネスチャットのログ(スクリーンショットやデータのエクスポートで保存)
- ※ 「言った言わない」を防ぐには、電話での重要なやり取りの後、「先ほどお電話でお話しした件ですが、以下の内容で進めますのでご確認ください」といった確認メールを送っておくことが極めて有効です。
- 写真・動画
- 追加・変更工事の施工前、施工中、施工後の写真。
- 定点カメラで撮影したり、日付が入るように設定したりすると、証拠価値が高まります。
- 客観的な記録
- 具体的に記載された作業日報
- 変更内容が反映された工程表
- 追加工事のために特別に発注した資材の納品書や領収書
弁護士に相談するメリット
追加・変更工事に関するトラブル予防や、発生してしまった紛争の解決において、弁護士は強力なパートナーとなります。
- 実用的な契約書・合意書の作成サポート: 弁護士に依頼すれば、貴社の業務実態に合わせてカスタマイズされた、法的に有効で実用的な追加工事合意書の雛形を作成することができます。
- 証拠の有効性の判断と交渉戦略の立案: トラブルが発生した際に、手元にある証拠が法的にどれほどの証明力を持つかを的確に判断し、それに基づいた最適な交渉戦略を立てることができます。
- 代理人としての交渉と法的手続きの遂行: 相手方が支払いに応じない場合、弁護士が代理人として交渉することで、円滑な解決が期待できます。交渉が決裂した場合には、内容証明郵便の送付から、調停、訴訟といった法的手続きまで、スムーズに移行し、貴社の権利実現をサポートします。
まとめ
追加・変更工事の代金請求を成功させる鍵は、「事前の明確な合意」と「その合意を証明する客観的な証拠」の2つに尽きます。
現場では、つい手間を惜しんで口約束で進めてしまいがちですが、その一時の手間を惜しんだがために、後で何倍もの時間と労力、そして本来得られるはずだった利益を失うことになりかねません。
「工事に着手する前に、必ず書面を残す」
この習慣を社内のルールとして徹底することが、将来の紛争から会社を守る最も確実な方法です。そして、もしトラブルが発生してしまった場合は、傷口が広がる前に、速やかに建設業に詳しい弁護士にご相談ください。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に