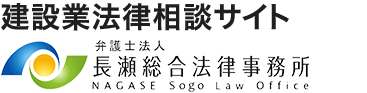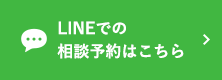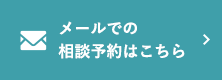2025/10/10 コラム
工事代金の支払いを拒否できる正当な理由とは?
はじめに
住宅の新築やリフォーム、あるいは事業用の建物の建設を依頼した際、完成した建物を見て「契約内容と違う」「欠陥があるのではないか」と不安に思い、工事代金の支払いに疑問を感じることがあるかもしれません。請負代金は高額になることが多く、納得できない状態での支払いは避けたいと考えるのは当然のことです。
しかし、単に「気に入らない」といった主観的な理由で、一方的に支払いを拒否することは、かえって建設業者とのトラブルを深刻化させ、法的な紛争に発展するリスクを伴います。では、どのような場合であれば、施主(注文者)は法的に「正当な理由」をもって工事代金の支払いを拒否、あるいは減額することが認められるのでしょうか。
この記事は、主に建設業者の皆様に向けて、2020年4月施行の改正民法を踏まえ、施主側がどのような法的根拠に基づいて支払いを拒否してくる可能性があるかを理解し、紛争を予防・解決するための知識を提供することを目的としています。施主の主張の妥当性を判断し、適切に対応するために、ぜひご一読ください。
Q&A
Q1: 施主から「イメージと違う」「質感が気に入らない」といった主観的な理由で、代金の支払いを保留されています。これに応じる必要はありますか?
応じる必要はありません。法律上、支払いを拒否できる正当な理由となるのは、契約内容との客観的な相違、すなわち「契約不適合」が存在する場合です。設計図書や仕様書、見積書などで具体的に定められた仕様(材質、色、寸法など)と明らかに異なる場合は契約不適合となりますが、単なる施主の主観的な「イメージ」との相違は、原則として法的な支払い拒否の理由にはなりません。このような主張に対しては、契約内容に基づき、仕様通りに施工されていることを丁寧に説明する必要があります。
Q2: 施主が、壁紙のわずかな傷やクロスの継ぎ目のわずかな隙間など、軽微な不具合を理由に代金全額の支払いを拒否しています。これは法的に認められますか?
認められる可能性は低いと考えられます。建物に何らかの契約不適合が存在する場合、施主は請負業者に対して、修補(追完)を請求したり、不適合の程度に応じて代金の減額を請求したりする権利があります。しかし、建物の価値を大きく損なうものではない軽微な契約不適合を理由に、請負代金「全額」の支払いを拒否することは、法的に「権利の濫用」と判断される可能性が高いです。このような場合は、まず該当箇所の修補を申し出るか、修補費用に相当する額の減額を協議することが現実的な解決策となります。
Q3: 施主が第三者の建築士を連れてきて、専門的な見地から多数の契約不適合を指摘し、支払いを拒否しています。どのように対応すればよいですか?
まずは冷静に、指摘された内容を一つ一つ書面で提示してもらうように求め、その内容を精査する必要があります。指摘が設計図書や仕様書に基づいた客観的な根拠のあるものか、それとも過剰な要求なのかを見極めなければなりません。自社での判断が難しい場合は、こちらも建築の専門家や弁護士に相談し、法的な観点から指摘内容の妥当性を検討することが不可欠です。相手の主張を鵜呑みにせず、証拠に基づいた対等な交渉を行う準備を進めるべきです。
解説
建設工事の請負契約は、請負人が仕事を完成させることを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬(請負代金)を支払うことを約束する契約です(民法632条)。したがって、工事が契約通りに「完成」すれば、注文者には原則として代金を支払う義務が発生します。
しかし、一定の「正当な理由」がある場合には、注文者はその支払いを一時的に拒んだり、減額を求めたりすることができます。建設業者の皆様は、施主からどのような主張がなされる可能性があるのかを理解しておくことが重要です。
支払いを拒否または減額できる「正当な理由」
施主が代金の支払いを拒否または減額できる法的な根拠は、主に以下の4つに分類されます。
工事が完成していない(債務不履行)
請負契約の根幹は「仕事の完成」です。契約で定められた工事が完了していない段階では、注文者に代金支払義務は発生しません。例えば、主要な工事が残っている、内装が全く手付かずであるなど、社会通念上「完成」とはいえない状態であれば、施主は代金の支払いを拒否できます。ただし、どこまでをもって「完成」と評価するかは、争いになりやすいポイントです。一般的には、最後の工程までが終了し、建物として使用できる状態になった時点をもって完成とされます。一部の軽微な手直しが残っているだけでは、「未完成」とは評価されにくい傾向にあります。
完成した建物に「契約不適合」がある
完成した建物が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない状態、いわゆる「契約不適合」である場合、施主は以下の権利を主張できます。これは2020年4月1日の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」から変更された考え方です。
- 追完請求権: 請負業者に対し、不適合部分の修補や代替物の引渡しを請求する権利です。これが施主の第一の権利となります。
- 代金減額請求権: 請負業者が相当の期間内に追完を行わない場合や、追完が不可能な場合に、不適合の程度に応じて代金の減額を請求する権利です。追完請求を経ずに、いきなり代金減額を請求することは原則としてできません。
- 損害賠償請求権: 契約不適合によって受けた損害(例えば、雨漏りによる家財の損害など)の賠償を請求する権利です。
- 契約解除権: 契約不適合により契約の目的を達成できない場合に、契約自体を解除する権利です。
重要なのは、契約不適合があるからといって、直ちに代金「全額」の支払いを拒否できるわけではないという点です。改正民法では、まず請負業者に修補等の機会を与える「追完請求」が原則とされており、これに請負業者が応じない場合に初めて「代金減額請求」が可能になるという、権利行使の順序が明確化されました。
工期が遅延したことによる損害が発生した
契約で定められた工期内に工事が完成せず、引き渡しが遅れた場合、それは請負業者の「履行遅滞」という債務不履行にあたります。この遅延によって施主に損害(例えば、仮住まいの家賃延長分、店舗の開業遅延による逸失利益など)が発生した場合、施主はその損害の賠償を請求できます。そして、この損害賠償請求権と、請負業者が持つ請負代金請求権を「相殺」する形で、実質的に支払額を減額することが可能です。ただし、天候不順や予期せぬ地中障害物の出現といった、請負業者の責めに帰すことができない事由(不可抗力)による遅延の場合は、損害賠償責任を負わない可能性があります。
同時履行の抗弁権
請負契約において、建物の「引渡し」と代金の「支払い」は、原則として同時に行われるべき関係(同時履行の関係)にあります(民法533条)。したがって、請負業者が建物の引渡しを拒んでいる場合には、施主も「引渡しがされるまでは代金を支払わない」と主張することができます。これは、支払いを一時的に拒む正当な理由となります。また、重大な契約不適合が存在し、請負人が追完義務を履行しない場合、これは「契約内容に従った履行の提供」がなされていない状態と評価できます。そのため、施主は同時履行の抗弁権を主張し、追完がなされるまで代金の支払いを拒むことができると考えられます。
「正当な理由」とはいえない主張の例
一方で、施主からのクレームの中には、法的には支払い拒否の理由として認められないものも多く含まれます。
- 契約内容となっていない主観的な不満: 「全体的な雰囲気がイメージと違った」「もっと高級感が欲しかった」といった、設計図書や仕様書に記載のない、施主の主観や感性に基づく不満は、原則として契約不適合にはあたりません。あくまで契約内容に適合しているか否かが判断基準となります。
- 過大な要求・権利の濫用: 前述の通り、ごく軽微な傷や汚れなどを理由に、請負代金全額の支払いを拒否するような行為は、権利の濫用とみなされる可能性があります。
- 施主側の都合による支払能力の欠如: 施主の資金繰りが悪化した、住宅ローン審査が通らなかったといった理由は、工事の出来とは無関係であり、代金の支払いを拒否する正当な理由にはなりません。
弁護士に相談するメリット
施主から代金の支払い拒否や減額要求を受けた場合、建設業者の皆様が弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 施主の主張の法的妥当性の判断: 施主からのクレームが、法的に見て「正当な理由」にあたるのか、それとも不当な要求なのかを専門家の見地から的確に判断できます。これにより、今後の対応方針を誤ることなく定めることができます。
- 証拠に基づく的確な反論: 弁護士は、契約書や設計図書などの証拠を精査し、施主の主張に対して法的な根拠に基づいた説得力のある反論を組み立てることができます。感情的な対立を避け、論理的に交渉を進めることが可能になります。
- 交渉の代理と紛争の早期解決: 当事者同士では感情的になりがちな交渉も、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静かつ建設的な話し合いが期待できます。また、必要に応じて調停や訴訟といった法的手続きに移行し、紛争の早期かつ適切な解決を図ります。
まとめ
施主が工事代金の支払いを拒否・減額できるのは、「工事の未完成」「契約不適合」「工期遅延による損害」「引渡し拒否への対抗(同時履行)」といった、法的に根拠のある「正当な理由」が存在する場合に限られます。
建設業者の皆様としては、施主からクレームや支払い拒否の意思表示があった場合、まずは慌てずに、その主張の根拠を具体的に確認することが重要です。そして、その主張が契約内容に照らして正当なものかを、客観的な証拠に基づいて冷静に判断する必要があります。
不当な要求に対しては毅然と対応し、正当な指摘に対しては誠実に対応するという姿勢が、無用な紛争を避け、最終的に自社の権利を守ることにつながります。施主との交渉が難航した場合や、法的な判断に迷った場合には、紛争が深刻化する前に、建設業に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に