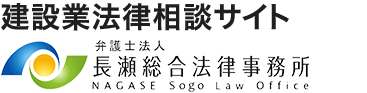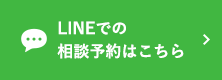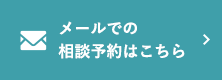2025/10/17 コラム
工事請負契約における「総価契約」と「単価契約」の違いと選択のポイント
はじめに
建設工事の請負契約を締結する際、請負代金をどのように決定するかは、契約全体の性質を左右する重要な要素です。その代表的な決定方法が、「総価契約(そうかけいやく)」と「単価契約(たんかけいやく)」です。これらは、どちらか一方が優れているというものではなく、工事の性質や規模、設計や仕様の確定度合いなど、案件の特性に応じて適切に使い分ける必要があります。
もし、工事の特性と契約方式がミスマッチを起こしてしまうと、どうなるでしょうか。例えば、仕様変更の際の金額交渉が著しく難航したり、実際に施工してみたら想定外の作業量が発生して採算が合わなくなったり、最終的な請負金額をめぐって発注者と深刻なトラブルに発展したりするリスクが高まります。
建設業者の皆様にとっては、それぞれの契約方式のメリット・デメリットを正確に理解し、案件ごとに最適な方式を提案・選択できる能力が、リスク管理と適正な利益確保の観点から重要な経営スキルといえるでしょう。
本記事では、「総価契約」と「単価契約」のそれぞれの特徴と法的な違い、そしてどのような場合にどちらを選択すべきかという実務的なポイントについて、弁護士が解説します。
Q&A
Q1: 「総価契約」と「単価契約」の最も大きな違いは何ですか?
大きな違いは、「請負代金の確定タイミング」と「算出方法」です。
- 総価契約(一式請負契約)
工事全体の完成を一つの目的とし、その対価として「工事一式 〇〇円」というように、契約時に最終的な支払総額を確定させる契約です。見積もりは、設計図書や仕様書に基づき、工事に必要な費用を積み上げて算出します。 - 単価契約
工事を構成する個々の作業項目(例:掘削1立方メートルあたり、配管1メートルあたり、特定の部材1個あたりなど)の「単価」をあらかじめ契約で決めておき、工事完了後に、実際に行った「数量」に基づいて最終的な代金を精算する契約です。契約時には総額は確定していません。
Q2: リフォーム工事を請け負う予定です。施主から「工事の途中で壁紙の色やキッチンのグレードなどを家族と相談しながら変えたくなるかもしれない」と言われています。この場合、どちらの契約方式が適していますか?
この場合、いくつかの選択肢が考えられます。
- 変更契約を前提とした総価契約: 基本的には総価契約としつつ、契約書に「仕様変更に関する条項」を明確に盛り込む方法が一般的です。「壁紙や床材、住宅設備などの仕様変更については、施主の希望に基づき別途見積書を提示し、双方が書面で合意(変更契約)した上で実施するものとする」と定めておくのです。これにより、当初の契約範囲と変更部分を明確に区別できます。
- 混合契約: もし、工事の大部分で仕様が未確定であるなど、変更の範囲が広範にわたる場合は、主要な構造部分などは総価契約とし、内装仕上げなど変更可能性が高い部分だけを単価契約(例:壁紙1平方メートルあたり〇円)とする混合契約も有効な選択肢です。
どちらの方法をとるにせよ、変更が生じる可能性を事前に施主に説明し、その場合の手続きと費用の考え方について共通認識を持っておくことが、後のトラブルを防ぐ上で重要です。
Q3: 当初は総価契約で契約しましたが、基礎工事を始めたところ、設計図書からは予測できなかった固い地盤や地中障害物が現れ、特別な重機を使った追加の地盤改良工事が発生しました。この代金はどのように請求すればよいですか?
A3: 総価契約は、原則として契約範囲内の作業であれば、たとえ予想より手間がかかったとしても、受注者がそのリスクを負うものです。しかし、ご質問のケースのように、契約時に当事者が想定していなかった事態(契約の前提を覆すような隠れた瑕疵や予期せぬ地中障害物など)に対応するための追加・変更工事は、元の総価契約の範囲外、つまり別の新たな契約として扱われるのが一般的です。
したがって、その追加工事については、まず工事を一旦止め、施主と別途協議の上、「追加工事合意書」などを取り交わし、代金を請求することになります。この際、追加工事部分については、その作業内容に応じて「掘削1立方メートルあたり〇円」といった形で単価で見積もりを提示し、合意を得るという、部分的に単価契約の考え方を用いるのが合理的かつ一般的です。勝手に工事を進めて事後請求すると、支払いを拒否されるリスクがあるので注意が必要です。
解説
総価契約と単価契約は、それぞれに一長一短があります。その特性を理解し、工事内容との相性を見極めることが、トラブルを未然に防ぎ、健全な経営を行うための鍵となります。
1 総価契約(一式請負契約)~計画性と効率性が利益を生む~
概要
「工事一式」に対して、総額いくらで請け負うかを契約時に確定させる方式です。英語ではLump Sum(ランプサム)契約とも呼ばれます。設計図書や仕様書に基づいて、工事全体に必要な材料費、労務費、現場経費、一般管理費、そして利益などを積み上げて総額を算出します。一般的な建築工事(新築の住宅、ビル、マンションなど)で広く採用されている、日本の建設業界におけるスタンダードな契約方式です。
メリット
- 発注者側: 支払う総額が契約時に確定するため、資金計画が立てやすく、予算オーバーのリスクを低減できるというメリットがあります。
- 受注者側: 発注者から合意を得た総額の範囲内で、企業の努力によってコストを削減できれば、その分が直接利益の増加につながります。技術革新や効率的な工程管理へのインセンティブが働きやすい契約方式です。
デメリット
- 発注者側: 契約内容が固定されるため、軽微な仕様変更でも、その都度、変更契約や追加費用の交渉が必要となり、柔軟性に欠けます。
- 受注者側: 見積もり時に予期せぬコスト増のリスク(資材価格の急騰、隠れた地中障害物の出現、想定外の補修工事など)を、原則としてすべて請負業者が負うことになります。見積もりの精度が低いと、赤字になるリスクを内包しています。また、仕様変更の際の代金交渉が難航しやすく、発注者との関係が悪化するきっかけにもなり得ます。
向いている工事
- 設計図書や仕様書が詳細に固まっており、工事内容が明確なもの(例:新築の戸建住宅、マンション、オフィスビル、設計施工分離方式の工事など)
- 工事の範囲や工程が事前に高い精度で予測できるもの
2 単価契約 ~透明性と柔軟性でリスクを分担~
概要
工事を構成する各工種・品目について、数量の単位(例:m、m²、m³、個、tなど)あたりの単価を契約時に決めておく方式です。工事完了後、実際に施工した数量を発注者立会いのもとで検収・測定し、その実績数量に契約単価を乗じて、最終的な請負代金額を確定させます。
メリット
- 発注者側: 実際の施工数量に基づいて支払いが行われるため、無駄がなく、契約の公平性・透明性が高いといえます。仕様変更や数量の増減にも柔軟に対応しやすいです。
- 受注者側: 数量の変動リスクを発注者が負うため、受注者側は「やってみたら想定よりはるかに数量が多かった(少なかった)」というリスクを回避でき、赤字リスクを低減できます。見積もりに要する手間や時間も、総価契約に比べて少ない場合があります。
デメリット
- 発注者側: 工事完了まで最終的な支払総額が確定しないため、予算管理が難しくなります。当初の概算予算を大幅に超えてしまうリスクがあります。
- 受注者側: 単価が固定されるため、契約期間中の急激な資材価格や労務費の変動リスクを負うことになります。また、発注者の都合で工事数量が大幅に削減されると、期待した売上が得られず、固定費を回収できない可能性があります。
向いている工事
-
- 工事完了までに仕様や数量が変動する可能性が高いもの
- 実際に施工してみないと正確な数量が把握できないもの(例:大規模な土木工事、トンネル工事、災害復旧工事、解体工事、地盤改良工事、遺跡調査に関連する工事など)
3 契約方式の選択と契約書作成の重要ポイント
どちらの契約方式を選択する場合でも、後々の「言った、言わない」というトラブルを防ぐために、契約書には以下の点を明確に記載することが重要です。
総価契約の場合
- 工事範囲の明確化: 「工事一式」の内訳を、設計図書、仕様書、見積書などを契約書の添付書類とする形で、可能な限り詳細に特定します。「一式」に含まれる業務と、含まれない業務(別途工事)の範囲を明確に線引きすることが、追加工事のトラブルを防ぐ上で重要です。
- 追加・変更工事のルール: 仕様変更や追加工事が発生した場合の手続き(協議の申し入れ、書面による合意、代金や工期の変更方法など)を具体的に定めておきます。
- 予期せぬ事態への備え: 天災地変や予期せぬ地中障害物など、不可抗力やリスクの分担に関する条項(危険負担)を設けておきます。
単価契約の場合
- 単価の適用範囲: 契約単価に何が含まれるのか(材料費、労務費、運搬費、現場管理費、一般管理費、利益など)を明確に定義します。これを「単価条件」と呼びます。
- 数量の測定・検収方法: 工事完了後、誰が、いつ、どのような方法で実績数量を測定し、確定させるのか、そのルールを具体的に定めておきます。測定方法をめぐる見解の相違は、トラブルの典型例です。
- 数量の大幅な変動への対応: 当初の想定から工事数量が大幅に増減した場合に、単価を見直すことができるか否か(スライド条項)を定めておくことが、双方にとって公平な契約となるために望ましいです。
弁護士に相談する具体的なメリット
最適な契約方式の提案
弁護士は、個別の工事案件の性質や潜在的なリスクを法的な観点から分析し、総価契約、単価契約、あるいはそれらを組み合わせたハイブリッド契約など、貴社にとって有利で、かつ公平な契約方式をアドバイスすることができます。
リスクを網羅した契約書の作成
選択した契約方式に応じて、将来発生しうるあらゆるトラブルを想定し、それを未然に防ぐための具体的な条項を盛り込んだ、実務に即した契約書を作成します。曖昧な表現をなくし、当事者双方の権利義務を明確にすることで、紛争の発生そのものを抑制します。
交渉のサポート
発注者との契約交渉において、なぜこの契約方式が適切なのか、なぜこの条項が必要なのかを、法的な根拠に基づいて説得的に説明するサポートを行います。力関係で不利になりがちな受注者の立場を守ります。
まとめ
「総価契約」と「単価契約」は、建設工事における請負代金の決定方法の二大方式です。それぞれの特徴をまとめると以下のようになります。
- 総価契約: 仕様が確定している工事に向き、受注者の効率化努力が利益に繋がりやすい。ただし、見積もり違いのリスクは受注者が負う。
- 単価契約: 数量が不確定な工事に向き、数量変動のリスクは発注者が負う。契約の透明性・公平性が高いが、予算が確定しにくい。
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、工事の特性に合わせて最適な方式を選択することが、適正な利益を確保し、無用な紛争を避けるための第一歩です。そして、どちらの方式を選択するにせよ、契約書においてそのルールを明確かつ具体的に定めておくことが重要です。
自社で扱っている工事の種類や、現在使用している契約書の内容に不安を感じる場合は、契約の専門家である弁護士に相談し、自社のビジネスモデルに合った、強固な契約基盤を構築することをお勧めします。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に