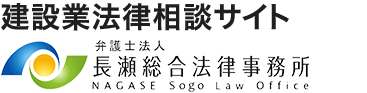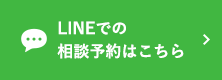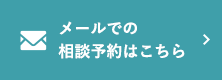2025/10/15 コラム
少額の工事代金未払いを回収するための最も効率的な方法とは?
はじめに
建設業界における代金未払い問題は、請負金額の大小を問わず、残念ながら日常的に発生します。特に、数万円から数十万円程度の「少額」な未払金は、多くの建設業者様を悩ませる根深い問題です。リフォーム工事の残代金、少しの追加工事の代金、メンテナンス費用などが、何かと理由をつけられて支払われないまま放置されているケースは決して少なくありません。
金額が少額であるため、「裁判を起こすほどの費用と手間はかけられない」「弁護士に依頼したら、回収額より費用の方が高くなる『費用倒れ』になってしまうのではないか」と考え、最終的に泣き寝入りしてしまっているのが実情ではないでしょうか。
しかし、一件一件は少額でも、それが積み重なれば会社の資金繰りを確実に圧迫する要因となります。さらに深刻なのは、一度支払いを免れる成功体験を相手に与えてしまうと、将来の取引においても同様のトラブルが繰り返されるリスクが高まることです。少額の未払いを放置することは、企業のコンプライアンス意識やリスク管理能力を疑われることにも繋がりかねません。
本記事では、このような少額の工事代金未払いを、「費用対効果」を意識しながら、いかにして「効率的」に回収するか、その具体的な方法と手順を、段階的なアプローチに沿って弁護士が解説します。
Q&A
Q1: 15万円の追加工事代金が未払いです。何度も電話していますが「担当者が不在」などと言われ、まともに取り合ってもらえません。弁護士に債権回収を依頼すると、費用倒れになるのではないかと心配です。
ご心配はもっともです。確かに、15万円の債権を回収するために、通常の民事訴訟を弁護士に依頼するとなると、着手金や報酬金を考慮すれば、費用倒れになる可能性は否定できません。しかし、弁護士の役割は訴訟だけではありません。
例えば、弁護士の名前で「内容証明郵便」を送付するだけで、相手方が事の重大さを認識し、速やかに支払いに応じるケースは非常に多くあります。この方法であれば、弁護士費用を数万円程度に抑えることが可能であり、費用対効果が高い手段です。
まずは費用を抑えた方法から試すなど、状況に応じた柔軟な対応をご提案できます。いきなり「訴訟」を考えるのではなく、「交渉」や「簡易な法的手続き」の専門家として、まずは一度弁護士にご相談ください。
Q2: 相手の会社の担当者と電話やメールでこれ以上話をするのが、精神的に大きな苦痛になっています。なるべく相手と直接関わらずに、簡単にお金を回収できる方法はありますか?
裁判所の手続きの中にも、相手と直接顔を合わせることなく、比較的簡易に進められるものがあります。その代表的なものが「支払督促」という手続きです。
これは、申立人の申立てに基づいて、裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる「支払督促」を送付してくれる制度です。手続きはすべて書類審査で進み、裁判所に出向く必要はありません。申立て手数料も、通常の訴訟の半額で済み、迅速な解決が期待できる効率的な方法です。
ただし、相手方がこの支払督促に対して異議を申し立てた場合は、通常の訴訟手続きに移行するという点には注意が必要です。しかし、相手と直接やり取りする精神的負担を軽減する第一歩として、有効な選択肢と言えるでしょう。
Q3: 「少額訴訟」という言葉を聞いたことがあります。これはどのような制度で、弁護士に依頼せず、自分自身で手続きを行うことは可能ですか?
はい、可能です。「少額訴訟」は、請求金額が60万円以下の金銭トラブルを解決するために用意された、特別な裁判手続きです。
最大の特徴は、原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決が言い渡されるという迅速さです。手続きも通常訴訟に比べて簡略化されており、訴状の雛形が裁判所のウェブサイトで公開されているなど、市民が本人で手続きを行うことが想定されています。
工事内容に不備があったなど、相手方が何らかの反論をしてくることが予想されるケースでも、裁判官に一度で白黒つけてほしい、という場合に有効です。少額債権の回収において、非常に使い勝手の良い制度の一つです。
解説
少額債権の回収で重要な視点は「費用対効果」です。時間、労力、そして金銭的なコストを最小限に抑えつつ、最大限の回収を目指すための戦略的なアプローチが求められます。ここでは、その具体的なステップを解説します。
まずは「裁判外」での効率的な回収を目指す(交渉・催告フェーズ)
最初から裁判所の手続きを考えるのは得策ではありません。まずは裁判外での交渉・催告から着手します。事を荒立てず、低コストで解決できるに越したことはないからです。
ステップ1:請求書の再発行と穏便な電話・メールによる確認
まずは、相手が単に支払いを忘れているだけ、あるいは経理上の手違いといった可能性も考慮し、事務的な確認として連絡を取ります。「〇月〇日付のご請求の件ですが、大変恐縮ながら、弊社の記録でご入金の確認ができておりませんでしたので、ご連絡いたしました」といった形で、あくまで穏便に切り出しましょう。請求書に「再発行」と明記して送付することも有効です。
重要なのは、この段階でのやり取りを必ず記録に残しておくことです。「いつ、誰が(自社の担当者)、誰に(相手の担当者)、どのような内容の連絡をしたか、そして相手がどう応答したか」を簡単なメモで良いので必ず記録しておきましょう。これが後の交渉や法的手続きで「支払いを求めていた証拠」となります。
ステップ2:内容証明郵便による最終催告
穏便な連絡を何度か行っても支払いに応じない、あるいは無視される場合は、次のステップとして「内容証明郵便」を送付します。これは、少額債権回収において、コストパフォーマンスの高い方法です。
- 心理的効果: 通常の手紙とは異なり、郵便局が内容と差出日を公的に証明してくれる特殊な郵便です。そのため、受け取った相手に「これは最終通告であり、次は弁護士や裁判所を介した法的手続きに進む」という強いプレッシャーを与えることができます。多くのケースでは、この段階で支払いに応じます。
- 費用対効果: 実費は郵便料金込みで2,000円程度です。行政書士や弁護士に文面の作成を依頼しても数万円程度で済むことが多く、訴訟に比べれば低コストです。
- 弁護士名の活用: 弁護士に依頼し、その法律事務所の名前で送付することで、「専門家が介入した」という事実が加わり、相手に与えるプレッシャーはさらに高まります。「弁護士費用がかかる前に支払った方が得策だ」と相手に判断させることが狙いです。
少額債権に特化した「裁判所」の手続きを活用する(法的措置フェーズ)
内容証明郵便を送ってもなお支払いがない、あるいは不当な反論を繰り返す悪質な相手の場合、いよいよ裁判所の手続きを利用します。少額債権の回収には、通常訴訟よりもはるかに効率的な、以下の2つの制度が用意されています。
方法1:支払督促 ~書類審査のみで迅速に~
概要: 申立人の申立てに基づき、裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる「支払督促」という公的な命令を送付する制度です。
メリット
- 迅速性: 裁判所に足を運ぶ必要がなく、書類審査だけで手続きが進みます。申立書が受理されれば、比較的速やかに相手方に支払督促が発送されます。
- 低コスト: 申立て手数料(裁判所に納める印紙代)が、同額を訴訟で請求する場合の半額で済みます。
- 強力な効果: 相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、申立人は「仮執行宣言」を得ることができます。この仮執行宣言が付いた支払督促は、確定判決と同じ効力を持ち、強制執行(給与や預金の差押え)が可能になります。
デメリット
- 相手が異議を申し立てると、通常の訴訟手続きに移行します。その場合、訴訟の半額だった手数料の差額分を追加で納める必要があります。
- 相手の住所・氏名(法人の場合は本店所在地・名称)が正確にわかっていないと利用できません。
向いているケース
相手に特に争う点(「工事に不備があった」など)はないはずだが、単に支払いを引き延ばしているような場合に、特に有効です。
■ 方法2:少額訴訟 ~1日で判決、白黒つける~
概要: 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、特別な訴訟手続きです。
メリット:
- スピード: 原則として1回の期日で審理が完了し、即日判決が言い渡されます。紛争の長期化を避けることができます。
- 簡便性: 手続きが簡素化されており、証拠もその場ですぐに調べられるものに限られます。弁護士に依頼せず、本人で訴訟を進めることが十分に想定されています。
- 柔軟な解決: 裁判官が間に入り、和解が推奨されることも多く、分割払いや支払猶予といった柔軟な内容で円満に解決することもあります。
デメリット
- 相手方が希望すれば、審理が複雑と判断された場合などに、通常訴訟に移行することがあります。
- 証拠書類(契約書、請求書、写真など)や証人は、審理の日にすぐに調べることができるように、事前にすべて準備しておく必要があります。準備が不十分だと不利な判決を受ける可能性があります。
向いているケース
相手が「追加工事の合意はしていない」「仕上がりに不満がある」など、何らかの反論をしてくる可能性があり、中立な裁判官に一度で白黒つけてほしい、という場合に有効です。
弁護士の効率的な活用法
少額債権の回収で弁護士に依頼するのは「もったいない」と思われがちですが、関与の仕方次第で、費用を抑えつつ効果を図ることが可能です。
- 法律相談(スポットコンサルティング)
まずは法律相談を利用し、自社の状況を説明して、どの手続きを選択すべきか、どのような証拠を集めればよいかといった、戦略的なアドバイスだけを受ける方法です。方針が決まれば、あとは自社で実行することで費用を抑えます。 - 内容証明郵便の作成・発送のみを依頼
弁護士の業務を、費用対効果の高い「内容証明郵便の送付」に限定して依頼します。弁護士名で送付するだけで解決する可能性に賭ける依頼方法です。この場合は書面作製代行となります。 - 本人訴訟のバックアップ(後方支援)
支払督促や少額訴訟の手続き自体はご自身で行い、訴状や申立書の作成方法、期日での主張の仕方、証拠の揃え方など、法的な部分だけを弁護士が後方で支援(バックアップ)する形です。これにより、費用を抑えながら、専門家のアドバイスを受けて有利に手続きを進めることができます。
まとめ
数万円、数十万円といった少額の工事代金未払いも、決して無視できる問題ではありません。「費用倒れになるから」と諦める前に、効率的な回収方法があることを知っておくことが重要です。
その手順は、
- まずは請求書再発行と電話・メールで穏便に確認(証拠は残す)
- 次に「内容証明郵便」を送付し、心理的圧力をかける
- さらに「支払督促」か「少額訴訟」を、状況に応じて選択する
という、段階的なアプローチが基本です。
一つ一つの債権を確実に回収する姿勢は、会社のキャッシュフローを健全に保つだけでなく、取引先との間に「この会社は支払いを疎かにすると、きっちり対応してくる」という健全な緊張感を生み、将来のトラブルを予防する効果もあります。
少額だからと一人で抱え込まず、費用を抑えた弁護士の活用法もありますので、泣き寝入りする前に、ぜひ一度、企業法務を扱う法律事務所にご相談ください。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に