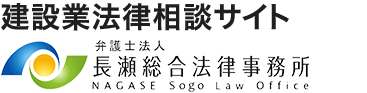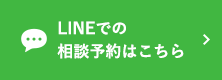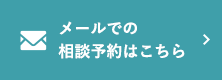2025/10/12 コラム
「言った言わない」を防ぐ!追加工事に関する合意書の作り方【雛形あり】
はじめに
建設工事において、追加・変更工事はつきものです。しかし、その代金支払いをめぐるトラブルもまた、頻繁に発生する悩ましい問題です。トラブルの根本原因のほとんどは、当事者間の「言った言わない」に集約されます。施主は「そんな指示はしていない」、請負業者は「確かに口頭で承諾を得たはずだ」。このような水掛け論を防ぐための強力なツールが、書面による「追加工事合意書」です。
建設業法第19条では、請負契約の締結に際して、一定の事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。追加・変更工事も、元の契約内容を変更する新たな契約であり、この定めに準じて書面を作成することが、コンプライアンスの観点からも極めて重要です。
本記事では、法的に有効で、かつ実務的にも使いやすい「追加工事合意書」に記載すべき項目と、その作成・運用上のポイントを、具体的な雛形を交えながら解説します。
Q&A
Q1: 毎回、正式な合意書を作成するのは手間がかかります。メールや簡単なメモではダメなのでしょうか?
メールやメモでも、合意内容が客観的に確認できれば、法的には証拠となり得ます。しかし、記載事項に漏れがあったり、内容が曖昧だったりすると、結局は「言った言わない」の争点を残すことになりかねません。後々のトラブル対応にかかる時間と労力を考えれば、必要な項目が網羅された合意書の雛形を準備しておき、それに沿って作成する方が、結果的に効率的で確実な方法といえます。
Q2: 追加工事の合意書や変更契約書に、収入印紙を貼る必要はありますか?
はい、必要になる場合があります。印紙税法上、元の工事請負契約書(課税文書)の重要な事項(請負金額など)を変更する契約書は、課税文書に該当します。貼付すべき印紙の税額は、契約書の記載方法によって大きく異なるため注意が必要です。
- 原則: 変更前の契約が特定でき、かつ変更契約書に「増額分」や「減額分」が明確に記載されている場合、その差額が記載金額となります。増額の場合はその金額に応じた印紙を、減額の場合は記載金額がないものとして200円の印紙を貼ります。
- 注意点: もし変更契約書に「変更後の契約金額総額」のみが記載され、増減額が明記されていない場合、その総額全体が記載金額とみなされ、印紙税額が高額になる可能性があります。節税の観点からも、増減額を明記することが重要です。不明な点は税務署や専門家にご確認ください。
Q3: この記事にある雛形を、そのままコピーして使っても問題ありませんか?
雛形は、一般的な追加・変更工事を想定した基本的なものですので、多くのケースでご活用いただけます。しかし、工事の内容が複雑であったり、特殊な条件が付いたりする場合には、雛形だけでは対応しきれない可能性があります。個別の事情に合わせて条項を追加・修正する必要がないか、必ず内容を検討してください。自社の業務に合わせてカスタマイズした雛形を作成したい場合や、重要な契約については、弁護士によるリーガルチェックを受けることをお勧めします。
解説
「追加工事合意書」は、未来の紛争を未然に防ぐための「保険」のようなものです。しっかりとした合意書を作成・保管しておくことで、万一の際に自社の正当性を証明し、会社を守ることができます。
追加工事合意書の法的意義と重要性
- 契約内容の明確化: 追加・変更工事の範囲、仕様、金額、工期などを書面で特定し、当事者間の認識の齟齬を防ぎます。
- 強力な証拠能力: 紛争が発生した場合、契約内容を証明する最も客観的で強力な証拠となります。
- 建設業法コンプライアンス: 法律(建設業法第19条)が求める書面交付義務を履行することにつながり、企業の信頼性を高めます。
- 紛争の抑止力: 書面による合意を求める姿勢を示すことで、相手方に対して安易な要求や後の紛争を思いとどまらせる心理的効果も期待できます。
合意書に必ず盛り込むべき10の記載事項
以下の項目は、建設業法第19条1項で定められた記載事項も踏まえており、これらを網羅することで、法的に有効で、紛争予防効果の高い合意書を作成することができます。
- 表題(タイトル): 「追加工事に関する合意書」「変更請負契約書」など、内容が分かるように記載します。
- 契約当事者の特定: 注文者(甲)と請負者(乙)の正式名称、住所を明記します。
- 元となる工事請負契約の特定: 「令和〇年〇月〇日付で締結した『〇〇邸新築工事請負契約』について」のように、どの工事に関する追加・変更なのかを明確にします。
- 追加・変更工事の具体的な内容: 最も重要な項目です。「別紙見積書No.〇〇及び別紙図面No.〇〇の通り」というように、詳細な仕様や範囲がわかる書類を添付する形が明確です。
- 追加工事代金: 追加・変更によって増減する金額を、消費税抜・税込の両方を明記すると親切です。
- 変更後の請負代金総額: 元の契約金額と追加代金を合算した、最終的な請負代金総額を記載します。
- 変更後の工期: 追加工事に伴い工期を延長する必要がある場合は、変更後の完成引渡日を必ず明記します。
- 追加代金の支払条件: いつ、どのような方法で支払うのか(例:最終金支払い時に合算して支払う、別途〇月〇日までに支払うなど)を定めます。
- 合意年月日: 当事者双方が合意した日付を記載します。
- 署名・捺印: 両当事者が記名し、押印します。法人の場合は、会社名、代表者役職、氏名を記載し、会社の実印(代表者印)を押印するのが望ましいといえます。
|
【雛形】追加工事請負契約合意書 追加工事請負契約合意書
注文者(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)は、甲乙間で令和●年●月●日付で締結した「(当初の工事名称)工事請負契約」(以下「原契約」という。)について、以下の通り追加・変更工事を行うことを合意する。
第1条(追加・変更工事の内容) 甲は乙に対し、以下の追加・変更工事(以下「本件追加工事」という。)を注文し、乙はこれを請け負う。 工事内容:別紙見積書(No. )及び別紙図面の通り。 工事場所:(原契約の工事場所と同じ)
第2条(追加請負代金) 本件追加工事の請負代金は、以下の通りとする。 金 ●●●,●●● 円 (消費税別) (消費税額 金 ●●,●●● 円) (合計金額 金 ●●●,●●● 円)
第3条(変更後の請負代金総額) 本件追加工事に伴い、原契約の請負代金を以下の通り変更する。 変更前請負代金:金 ●,●●●,●●● 円(消費税込) 変更後請負代金:金 ●,●●●,●●● 円(消費税込)
第4条(変更後の工期) 本件追加工事に伴い、原契約の工期を以下の通り変更する。 変更前工期:令和●年●月●日 まで 変更後工期:令和●年●月●日 まで
第5条(追加代金の支払) 甲は乙に対し、第2条に定める追加請負代金を、原契約に定める最終代金の支払日に、合算して支払うものとする。
第6条(原契約の適用) 本合意書に定めのない事項については、すべて原契約の各条項が適用されるものとする。
上記合意の証として、本書面を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
(甲)注文者 住所: 氏名: 印
(乙)請負者 住所: 商号: 代表者: 印 |
合意書作成・運用のポイントと注意点
- 着手前の作成を徹底: 合意書は、必ず追加工事に着手する「前」に作成・締結してください。工事が進んでからでは、交渉力が低下し、不利な条件を飲まざるを得なくなる可能性があります。
- 誰が読んでも分かるように: 工事内容や金額は、専門家でなくても理解できるよう、具体的かつ平易な言葉で記載しましょう。曖昧な表現はトラブルの元です。
- 原本の保管: 締結した合意書は、原契約書と一緒に、工事完了後も紛争が起こりうる期間(契約不適合責任の期間など)は、確実に保管してください。
- 電子契約の活用: 頻繁に追加・変更工事が発生する場合、書面の作成・郵送・返送・保管は大きな負担になります。クラウド型の電子契約サービスを導入すれば、これらのプロセスをオンラインで完結でき、業務効率化とコスト削減、コンプライアンス強化につながります。また、電子契約は印紙税が不要となるため、コスト削減のメリットもあります。
弁護士に相談するメリット
- 自社に最適化された雛形の作成: 弁護士に相談すれば、本記事で紹介したような一般的な雛形をベースに、貴社の事業内容や取引の特性に合わせた、より実践的でリスク回避能力の高い合意書の雛形を作成することが可能です。
- 個別案件のリーガルチェック: 特に、請負金額が高額な追加工事や、内容が複雑で将来的なリスクが懸念される案件については、契約を締結する前に弁護士によるリーガルチェックを受けることで、不利な条項や潜在的なリスクを事前に発見・修正することができます。
- 署名拒否等への対応策: 相手方が合意書への署名を渋ったり、不当な条件を要求してきたりした場合に、どのように交渉を進めるべきか、法的な観点から具体的なアドバイスを受けることができます。
まとめ
「言った言わない」の泥沼の争いを防ぐための最善策は、面倒でも「着手前に書面で合意する」という原則を徹底することです。追加工事合意書は、単なる事務手続きではなく、貴社の正当な利益と権利を守るための重要な法的文書です。
今回ご紹介した雛形と記載事項を参考に、自社でのルールを確立し、書面作成を習慣化してください。それが、施主や元請業者との健全な信頼関係を築き、安定した事業運営を行うための礎となります。
関連動画のご案内
長瀬総合法律事務所では、企業法務や建設業界に関する法的知識をより深く理解するための動画をYouTubeで配信しています。建設業向け顧問弁護士サービスの詳細や、具体的なケーススタディも取り上げていますので、ぜひご視聴ください。
顧問サービスのご案内
契約書の確認から労務問題、トラブル対応まで、リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開するためのサポートをご用意しております。
お問い合わせ
ご相談はお気軽に